
ホーム/KJDNKTK2025
かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会 2025


「六行会ホールでどのような『ダンス』がつくれますか?」
あらゆる制約抜きにかつてなく自由なダンスの企画案を提案
2年目!に進出した3組が企画の作品化をかけて挑む最終プレゼンテーション
「六行会ホールでどのような『ダンス』をつくれますか?」をお題として、アーティスト6組がダンス作品のドリームプラン(予算や実現可能性度外視の企画案)を公開プレゼンテーションした昨年の「KJDNKTK2024」。ディレクターにより選出された3組が企画の作品化をかけて挑む最終プレゼンテーション。かつてなく自由に!
黄倉未来によるエキシビジョンパフォーマンス&幕間には今年もMC��担当のテニスコーツによるミニライブも開催
日時:2025年4月20日(日)15:30開演
※受付開始は15:00 ※終演時間は19:30頃を予定
会場:六行会ホール(東京都・品川区)

参加アーティスト:
JACKSON kaki
豊田ゆり佳
涌井智仁
エキシビジョンパフォーマンス:黄倉未来「フリースタイル落語」

ゲストMC:Tenniscoats/テニスコーツ
幕間でミニライブあり!!!

ディレクター|審査員
塚原悠也(アーティスト/contact Gonzo)
志賀理江子(写真家)
やんツー(美術家)

料金:3,500円 ※当日券は+500

会場:六行会ホール
〒140-0001 東京都品川区北品川2丁目32-3
京急本線「新馬場駅」 北口から徒歩3分


Nextream21
かつてなく自由にダンスを名乗るための煙が立つ会(KJDNKTK)
「ダンス」をかつてなく自由につくりだすアーティストを輩出するためのプログラム。2024年に始動し「六行会ホールでどのような『ダンス』をつくれますか?」というお題での企画案を公募。選出された6組が公開プレゼンテーションを実施。
今年2年目への進出者3組が選抜され、ディレクションチームをメンターとするクリエーションで企画案を実現可能なものに更新。本イベント「KJDNKTK2025」にて再び公開プレゼンテーションを実施し、3年目に進出する1組を選出。最終年はたった1組の参加アーティストとディレクションチームのトライ&エラーで六行会ホールを会場とした作品発表を行うもの。

表現者が束になって自由に思考・実践する必要がある。煙が立てば観にいこう。褒められる必要はない。餌を持つ手を噛むタイミング、それ考えよう。
5年後? 10年後? 15年後?人類が想像もしなかったような表現形式がダンスの一形態として認識される。表現者が束になって自由に思考・実践する必要がある。ただし従来の形式の中で只々コンテンツを作っていても進まない。歴史を振り返れば、優れた芸術家は常にその形式を支える構造、ハードを触り、形式を改変して社会に投げつけてきたことは調べればすぐにわかる。音楽、絵画、彫刻、文学、演劇、ダンス、それぞれの分野で通常の思考では想像できないような更新が定期的に起こっている。もちろんその度に「これは○○ではない」というお決まりの批判も起こっただろうが、本来芸術家が日々思考していることはそんなところに留まらないはずである、ということを知ってしまった 。むしろこの批判を定点観測すべきであり、芸術家ならそこを狙うくらいがちょうどいい。煙が立てば観にいこう。褒められる必要はない。餌を持つ手を噛むタイミング、それ考えよう。それに続いて混乱と反乱を生み出すのが仕事である。現在の価値、正義のあり方を平然と疑い実践を進めるべきである。今日、資本によってイケてる「文化」らしきものが乱立する世の中において、そのような芸術を実践するのは非常に困難な事ではあるが、その上であえてコケることなどによって一つ二つタガを外せば必ず景色は変わる。人類の認知領域を少しでも広げるのはこの地球上で活動する芸術家の集団的な任務であり、それは人類が宇宙開発を進める事と同等の価値があり、芸術家として存在することに対する宿命である。
塚原悠也(KJDNKTK代表ディレクター)

アーティスト/企画案



JACKSON kaki
1996年静岡県生まれ、情報科学芸術大学院大学在籍。アーティスト、DJ、VJ、映像作家、グラフィッ クデザイナーとして活動する。VR/AR、3DCG、映像、パフォーマンス、インスタレーション、サウンド など、マルチメディアを取り扱い、身体の自然と、バーチャル・リアリティーの概念について制作とリ サーチを行う。
テクノロジーダンス「さるかに合戦」
暴力・性・死を描くために、テクノロジーと「さるかに合戦」を踊ります。
本パフォーマンスはテクノロジーと物理現実の肉体を用いて、「隠された身体」つまり「暴力」「性」「死」について、伝統的な物語である「さるかに合戦」に沿いながら、ダンスを踊ります。私たちから隠されている身体を剝き出しにしながら、それを隠そうとするテクノロジーと共に「必死に」踊ります。



豊田ゆり佳
1999年生まれ。4歳よりクラシックバレエを始める。2017年 立教大学現代心理学部映像身体学科入学。振付家・ダンサーの砂連尾理に師事。 2021 年東京藝術大学美術研究科先端芸術表現専攻入学。2023 年パリ国立高等美術学校 ( École Nationale Supérieure des Beaux-Arts) に交換留学。
ドMの極み
舞台という空間にどれだけ居続けられるか、あるいは居たいと思えるかの実験。
舞台という非日常的な空間に” ダンサーやパフォーマー” と呼ばれる人々を無造作におき、どのように振る舞うか、あるいは挫折するか、あるいは逃げ出すか実験する。何があっても舞台に立ち続けることができるものが真のダンサー/パフォーマーであるとした場合、マゾヒズムの心を持って実験に挑む必要がある。



涌井智仁
1990年新潟県(日本)生まれ。東京都(日本)在住。美術家、音楽家、キュレーター。オルタナティブ・スペースであるWHITEHOUSEのディレクター兼キュレーターとして、アンコントローラブルな総合芸術の場の生成を構想してる。主にジャンクパーツやAV機器を用いてテクノロジーの進化の中で捨て置かれた「有機性」を表現している。主な展覧会は、「Junk's Ports」ANOMALY,2023、「電気-音」金沢21世紀美術館,2023、「How to face our problems」代官山ヒルサイドテラス,2023
まひをどりのまに
我々が回転することと地球の回転。そして、我々が跳ぶことと重力、光のトリロジー。
民俗学者の折口信夫によって1952年に書かれた短い論考「舞ひと踊りと」の中で展開された、旋回運動としての「まひ」と跳躍運動としての「をどり」、という2つのフォームの在り方をヒントに現代ダンスを捉え返すプロジェクト。そして、ダンスを踊れないわたしが、まひをどりの「ま」の中に佇んでダンスを激しく見つめ、最終的にからだが動くまでのたった1つの長いダンス。

黄倉未来
音楽家、あるいは非音楽家。
バラエティ番組「サイコラキー」制作、フリースタイル落語独演会、ゴアトランスレーベル「CYBER ACID RAVE PEOPLE(C.A.R.P.)」主宰など。



テニスコーツ
1996年頃結成。さや(ヴォーカルほか)と植野隆司(ギターほか)によるバンド。国内外の多数のレーベルからの作品発表やツアー・ライブを重ね、さまざまなバンドやミュージシャンとのコラボレーションも多数。長年のキャリアがありながらも、いつも結成当初のような状態で、まったく型にはまらない温かくもクールな活動と演奏を続けている。

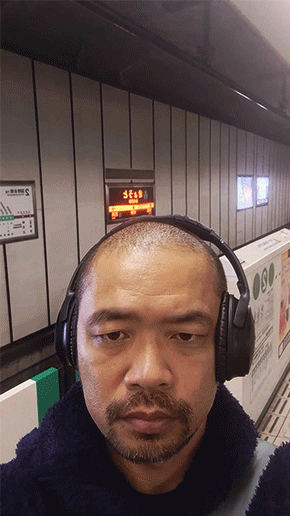

(アーティスト/contact Gonzo メンバー)代表ディレクター
関西学院大学文学部美学専攻修士課程修了後、NPO法人ダンスボックスのスタッフを経て、2006年パフォーマンス集団「contact Gonzo」の活動を開始し国内外で作品を発表。個人として2020年演劇作品『プラータナー:憑依のポートレート』におけるセノグラフィと振付に対し「読売演劇大賞」スタッフ賞受賞。現KYOTO EXPERIMENT共同ディレクター。


(写真家)ディレクター
2008年宮城県に移り住み、その地に暮らす人々と出会いながら、人間社会と自然の関わり、死の想像力から生を思考すること、何代にも溯る記憶などを題材に制作。2011年、東日本大震災での沿岸部における社会機能喪失や、厳格な自然法則の体験は、その後の「復興」に圧倒されるという経験に結びつき、人間精神の根源を、様々な制作によって追及しようとした。
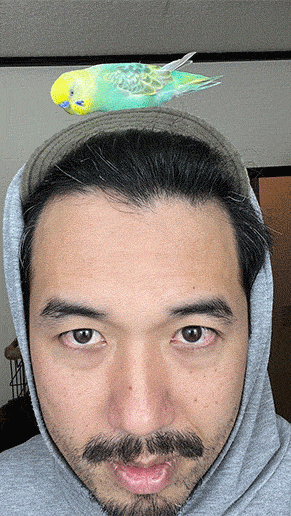

(美術家)ディレクター
1984年、神奈川県生まれ。絵を描く、文字を書く、鑑賞するなど、人間特有と思われるような行為を、機械に代替させる作品で知られる。近年の主な展覧会に、「六本木クロッシング2022展:往来オーライ!」(森美術館、東京、2022)「遠い誰か、ことのありか」(SCARTS、札幌、2021)などがある。
クレジット
舞台監督:湯山千景 音響:齊藤梅生 照明:久津美太地 映像:須藤崇規
協力:小声 宣伝美術:小池アイ子
プロデューサー:花光潤子(NPO法人魁文舎) 企画制作:林慶一 当日運営:岩中可南子、小泉実樹、岸本茉夕





